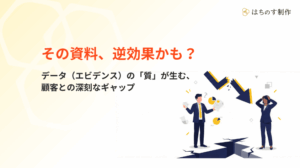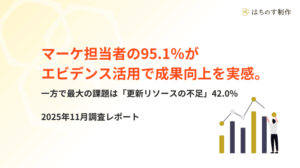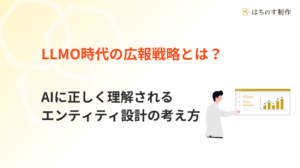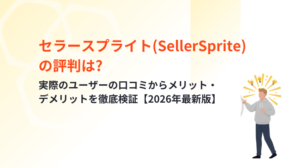【完全版】リード獲得方法20選!BtoB/オンライン施策からKPI設定・最新ABM戦略まで徹底解説
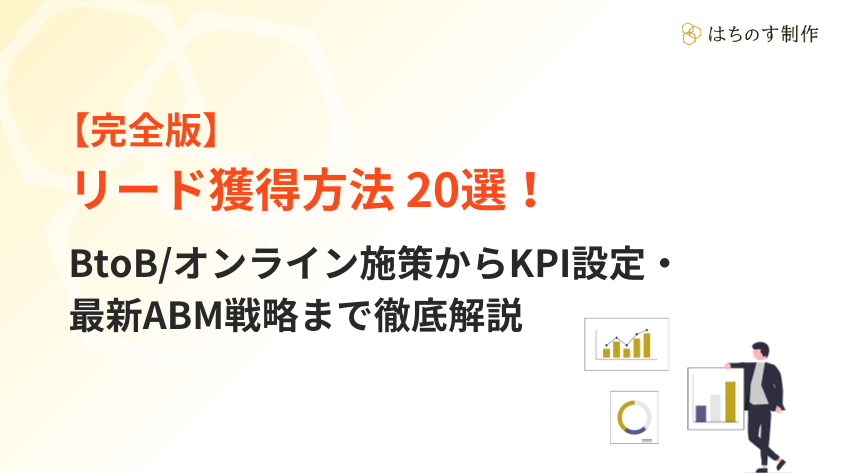
企業の成長戦略において、「リード獲得」は避けて通れない重要なテーマです。
新規顧客を獲得し、売上を向上させるためには、効果的なリード獲得戦略が不可欠となります。
しかし、マーケティング手法が多様化する現代において、「どのような方法でリードを獲得すれば良いのか」「自社に最適な戦略は何か」とお悩みのマーケティング担当者、営業担当者、経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、リード獲得の基本的な知識から、オンライン・オフラインの具体的な手法20選、さらにはBtoBに特化した最新のABM戦略、成功のためのポイント、役立つツールまで、リード獲得に関する情報を網羅的に解説します。
この記事を読めば、リード獲得に関する疑問が解消され、自社に最適な戦略を見つけ、実践への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
弊社独自調査による『AI時代のSEO最新情報』資料を、下記ページよりダウンロードいただけます。まず理解すべき「リード獲得」の基本:目的と全体像
リード獲得戦略を考える前に、まずは「リード」とは何か、そしてなぜリード獲得が重要なのか、その基本的な概念を理解しておくことが大切です。
ここでは、リード獲得の定義、目的、そしてマーケティング・営業活動全体における位置づけについて解説します。
リード(見込み顧客)とは?種類と定義をわかりやすく解説
リード(Lead)とは、一般的に「見込み顧客」と訳されます。
これは、自社の製品やサービスに何らかの興味関心を示しており、将来的に顧客になる可能性のある個人や企業の情報を指します。
具体的には、ウェブサイトからの問い合わせ、資料請求、セミナー参加、名刺交換などで得られた連絡先情報などがリードにあたります。
リードは、その関心度や購買意欲の高さによって、いくつかの種類に分類されることがあります。
代表的なものとしては、以下の2つがあります。
- MQL(Marketing Qualified Lead)
マーケティング活動によって創出されたリード。マーケティング部門が育成対象と判断したリードを指します。まだ購買意欲は低いものの、将来的に顧客になる可能性がある層です。 - SQL(Sales Qualified Lead)
営業活動の対象となるリード。マーケティング部門による育成を経て、購買意欲が高まり、営業担当者がアプローチすべきだと判断されたリードを指します。具体的な商談に進む可能性が高い層です。
リードの種類を理解し、それぞれの段階に応じたアプローチを行うことが、効率的な営業・マーケティング活動につながります。
なぜリード獲得が重要なのか?企業成長における目的と役割
企業が成長し続けるためには、新規顧客を獲得し、売上を拡大していく必要があります。
リード獲得は、その最初のステップであり、将来の顧客候補を見つけ出す活動です。
リード獲得の主な目的と役割は以下の通りです。
- 新規顧客獲得の起点
新しいビジネスチャンスを創出するための出発点となります。 - 売上向上の基盤
獲得したリードを育成し、顧客化することで、安定的な売上につながります。 - 営業活動の効率化
質の高いリードに絞ってアプローチすることで、営業担当者の負担を軽減し、成約率を高めることができます。 - 市場での競争力維持
競合他社に先んじて有望な見込み顧客との接点を持つことで、市場における優位性を確保します。
このように、リード獲得は単なる情報収集ではなく、企業の持続的な成長を支えるための戦略的な活動なのです。
リード獲得から顧客化までの全体像(マーケティングファネル)
リード獲得は、顧客を獲得するための一連のプロセスの一部です。
一般的に、顧客獲得までの流れは「マーケティングファネル」という考え方で説明されます。
ファネル(漏斗)のように、段階が進むにつれて対象者の数が絞られていく様子を表しています。
マーケティングファネルは、大きく以下の段階に分けられます。
- リードジェネレーション(Lead Generation)
見込み顧客(リード)を獲得する段階。本記事の主要テーマです。 - リードナーチャリング(Lead Nurturing)
獲得したリードを育成する段階。メールマガジンやセミナーなどを通じて、リードとの関係性を構築し、購買意欲を高めます。 - リードクオリフィケーション(Lead Qualification)
育成したリードの中から、購買意欲が高く、営業がアプローチすべきリードを選別する段階。スコアリングなどの手法が用いられます。 - 商談・顧客化
選別されたリードに対して営業がアプローチし、商談を経て顧客へと転換させる段階。
この全体像を理解することで、リード獲得が単なる入り口に過ぎず、その後の育成や選別プロセスと連携して初めて成果につながることが分かります。
【網羅版】リード獲得方法20選:オンライン・オフライン施策を徹底比較
リードを獲得するための具体的な方法は多岐にわたります。
大きく分けると、インターネットを活用する「オンライン施策」と、対面や郵送などを用いる「オフライン施策」があります。
ここでは、代表的なリード獲得方法を合計20種類、オンライン・オフラインに分けてご紹介します。
それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合わせて組み合わせることが重要です。
オンラインでのリード獲得方法12選
デジタル技術の発展に伴い、オンラインでのリード獲得手法はますます多様化・高度化しています。
ここでは、主要なオンライン施策を12種類ご紹介します。
1.コンテンツマーケティング(ブログ・SEO)
自社ブログやオウンドメディアで、ターゲット顧客にとって価値のある情報(課題解決策、ノウハウ、事例など)を発信し、検索エンジン経由(SEO)での集客を狙う方法です。
質の高いコンテンツは、企業の専門性を示し、信頼性を高める効果があります。
継続的な情報発信により、長期的な資産となるリード獲得チャネルを構築できます。
2.ホワイトペーパー・資料ダウンロード
調査レポート、ノウハウ集、導入事例集などの有益な資料(ホワイトペーパー)を作成し、Webサイト上で公開します。
ダウンロードする際に、氏名や連絡先などの情報を入力してもらうことでリードを獲得します。
ターゲットの課題解決に直結するような魅力的な資料を用意することがポイントです。
3.Web広告(リスティング・ディスプレイ)
GoogleやYahoo!などの検索結果に表示されるリスティング広告や、Webサイトの広告枠に表示されるディスプレイ広告を活用する方法です。
特定のキーワードやターゲット層に絞って広告を表示できるため、即効性のあるリード獲得が期待できます。
ただし、継続的な広告費用が発生します。
4.SNS広告(Facebook, Instagram, LinkedInなど)
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedInなどのSNSプラットフォームに出稿する広告です。
詳細なターゲティング設定が可能で、特定の興味関心を持つ層や、特定の属性を持つユーザーに効率的にアプローチできます。
プラットフォームの特性に合わせたクリエイティブが重要です。
5.動画広告(YouTubeなど)
YouTubeなどの動画プラットフォームで配信される広告です。
視覚と聴覚に訴えかけることで、製品やサービスの魅力を効果的に伝えられます。
スキップ可能な広告や、動画本編前に流れる広告など、様々な形式があります。
ブランディング効果も期待できます。
6.ウェビナー(オンラインセミナー)
インターネットを通じて開催するセミナー(ウェビナー)です。
特定のテーマに関心のある参加者を集め、専門知識やノウハウを提供します。
参加申し込み時にリード情報を獲得でき、質疑応答などを通じて直接的なコミュニケーションも可能です。
場所を選ばずに開催・参加できるメリットがあります。
7.メールマーケティング(メルマガ)
既存のメールリストに対して、定期的にメールマガジン(メルマガ)やキャンペーン情報を配信する方法です。
有益な情報を提供し続けることで、休眠顧客の掘り起こしや、既存顧客からの追加リード獲得につなげることができます。
パーソナライズされたメールは開封率・クリック率を高めます。
8.SNS運用(オーガニック)
企業の公式SNSアカウント(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInなど)を運用し、情報発信やユーザーとのコミュニケーションを通じてファンを増やし、リード獲得につなげる方法です。
広告費はかかりませんが、継続的な運用と魅力的なコンテンツ作成が必要です。
9.プレスリリース配信
新製品の発売、事業提携、イベント開催などの企業ニュースを、プレスリリース配信サービスを通じてメディアに配信する方法です。
メディアに取り上げられることで、認知度向上や信頼性向上につながり、間接的にリード獲得に貢献します。
10.外部メディア掲載・タイアップ記事
業界専門メディアやニュースサイトなどに、自社に関する記事を掲載してもらう、または広告として記事を作成(タイアップ記事)する方法です。
メディアの読者層に直接アプローチでき、第三者視点での紹介は信頼性を高めます。
11.比較サイト・口コミサイト活用
製品やサービスの比較サイトや口コミサイトに情報を掲載したり、ユーザーレビューを促進したりする方法です。
購買検討段階にあるユーザーからのリード獲得が期待できます。
ポジティブな評価を集めることが重要です。
12.オンラインイベント・バーチャル展示会
オンライン上で開催されるカンファレンスや展示会に参加・出展する方法です。
ウェビナーと同様に、地理的な制約なく多くの参加者を集めることができます。
仮想ブースでの資料配布やチャット機能を通じてリードを獲得します。
オフラインでのリード獲得方法8選
オンライン施策が主流となりつつありますが、オフライン施策も依然として有効なリード獲得手段です。
特に、直接的なコミュニケーションが求められる場合や、特定のターゲット層にアプローチしたい場合に効果を発揮します。
13.展示会・見本市
業界関連の展示会や見本市にブースを出展する方法です。
製品やサービスに関心を持つ来場者と直接対話し、名刺交換などを通じてリードを獲得できます。
製品デモや体験コーナーを設けることで、より深い理解を促せます。
出展費用や準備にコストと時間がかかります。
14.セミナー・カンファレンス(自社開催・共催)
自社でセミナーやカンファレンスを企画・開催、または他社と共催する方法です。
特定のテーマに関心のある参加者を集め、専門知識を提供することで、質の高いリードを獲得できます。
参加者との質疑応答や懇親会を通じて、関係性を深めることも可能です。
集客が成功の鍵となります。
15.ダイレクトメール(DM)・FAXDM
ターゲットとなる個人や企業に対して、郵送でパンフレットやカタログ、案内状などを送付する方法(DM)、またはFAXで案内を送る方法(FAXDM)です。
特定のリストに基づいて送付するため、ターゲットを絞りやすいのが特徴です。
開封されやすいデザインや、魅力的なオファーが重要になります。
印刷・郵送コストがかかります。
16.テレアポ(アウトバウンドコール)
ターゲットリストに基づいて、電話で直接アプローチし、アポイントメント獲得や資料送付の承諾などを目指す方法です。
直接対話できるため、相手の反応を見ながら柔軟に対応できます。
ただし、担当者につながりにくかったり、断られたりすることも多く、オペレーターのスキルが求められます。
17.マス広告(テレビCM・新聞・雑誌)
テレビCM、新聞広告、雑誌広告など、不特定多数の人々に向けて情報を発信する広告手法です。
広範囲に認知度を高める効果がありますが、費用が高額になる傾向があります。
BtoC商材や、ブランドイメージ向上を目的とする場合に有効です。
18.交通広告・屋外広告(OOH)
電車内の広告、駅のポスター、街中の看板、デジタルサイネージなど、公共交通機関や屋外スペースに掲出する広告(Out Of Home)です。
特定の地域や路線を利用する人々に繰り返し訴求できます。
視認性の高いデザインが重要です。
19.紹介(リファラル)
既存顧客や取引先、パートナー企業などから、新たな見込み顧客を紹介してもらう方法です。
紹介者からの信頼があるため、成約率が高い傾向にあります。
紹介プログラムやインセンティブを用意することで、紹介を促進できます。
コントロールが難しい側面もあります。
20.飛び込み営業
事前の約束なしに、企業や個人宅を直接訪問して営業活動を行う方法です。
新規開拓の手法の一つですが、効率が悪く、相手に敬遠される可能性も高いです。
特定の業種や地域密着型のビジネスで用いられることがあります。
| 施策の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| オンライン | ・広範囲にリーチ可能 ・詳細なターゲティングが可能 ・効果測定が容易 ・比較的低コストで始められる施策が多い ・時間や場所の制約が少ない | ・競合が多い ・情報が流れやすい ・直接的な信頼関係構築が難しい場合がある ・インターネットを利用しない層には届きにくい |
| オフライン | ・直接的なコミュニケーションによる信頼関係構築 ・五感に訴える体験を提供可能 ・特定の地域や層に集中アプローチ可能 ・記憶に残りやすい | ・リーチできる範囲が限定的 ・効果測定が難しい場合がある ・オンライン施策に比べてコストが高い傾向 ・時間や場所の制約が大きい |
【潜在ニーズに応える】自社に最適なリード獲得方法の選び方:5つの視点
数あるリード獲得方法の中から、自社にとって最も効果的な方法を選ぶには、どのような点を考慮すれば良いのでしょうか。
ここでは、潜在的なニーズである「自社に合った、最も効果的で効率の良いリード獲得方法を見つけたい」という思いに応えるため、5つの視点から最適な方法を選ぶための考え方をご紹介します。
1.ターゲット顧客(ペルソナ)は明確か?
まず最も重要なのは、どのような顧客にアプローチしたいのか、ターゲット顧客像(ペルソナ)を明確にすることです。
- ターゲット顧客はどのような課題やニーズを持っているのか?
- 普段、どのようなチャネルで情報収集しているのか?(Webサイト、SNS、業界誌、展示会など)
- どのような情報に関心を持つのか?
ペルソナが明確であれば、そのペルソナが利用する可能性の高いチャネルや、響きやすいメッセージを特定しやすくなります。
例えば、IT系のエンジニアであれば技術ブログやオンラインコミュニティ、経営者層であればビジネス系メディアや展示会、セミナーなどが有効な接点となる可能性があります。
2.BtoBかBtoCか?ビジネスモデルによる違い
企業向け(BtoB)か、一般消費者向け(BtoC)かによって、有効なリード獲得方法は大きく異なります。
- BtoB
- 検討期間が長く、意思決定に関わる人が複数いることが多い。
- 論理的な判断や費用対効果が重視される傾向がある。
- ホワイトペーパー、ウェビナー、展示会、LinkedInなどが有効。
- BtoC
- 検討期間が比較的短く、個人の感情や流行に影響されやすい。
- 共感やブランドイメージが重要になることが多い。
- SNS広告、インフルエンサーマーケティング、Web広告、キャンペーンなどが有効。
自社のビジネスモデルに合わせて、適切なアプローチを選択しましょう。
3.予算とリソースはどれくらいか?費用対効果の考え方
リード獲得には、当然ながら予算と人的リソースが必要です。
各施策には、それぞれ異なるコスト(広告費、ツール利用料、制作費、人件費など)がかかります。
- 限られた予算で始めるなら、コンテンツマーケティング(SEO)やSNS運用など、低コストで始められる施策から検討する。
- 即効性を求めるなら、Web広告やテレアポなど、比較的短期間で成果が出やすい施策に予算を投下する。
- 人的リソースが不足している場合は、ツールを活用したり、外部の支援サービスを利用したりすることも検討する。
また、単にコストだけでなく、リード獲得単価(CPL: Cost Per Lead)や顧客獲得単価(CPA: Cost Per Acquisition)、投資対効果(ROI)を算出し、費用対効果の高い施策を見極めることが重要です。
4.商材・サービスの特性(価格帯、複雑性)に合っているか?
扱っている商材やサービスの特性も、リード獲得方法を選ぶ上で重要な要素です。
- 高価格帯・複雑な商材
- 顧客は慎重に情報収集し、比較検討する傾向がある。
- 詳細な情報提供や、信頼関係の構築が重要。
- ホワイトペーパー、ウェビナー、セミナー、事例紹介、個別相談などが有効。
- 低価格帯・シンプルな商材
- 衝動的な購買や、手軽さが求められる場合がある。
- 認知度向上や、お得感をアピールすることが重要。
- Web広告、SNSキャンペーン、クーポン配布などが有効。
商材の特性に合わせて、顧客が求める情報やアプローチ方法を考えましょう。
5.短期的な成果か、長期的な資産構築か?
リード獲得戦略を考える際には、時間軸も考慮に入れる必要があります。
- 短期的な成果を求める場合
- Web広告、SNS広告、テレアポ、展示会など、比較的早く結果が出やすい施策が中心となります。
- ただし、継続的なコストが発生したり、効果が一時的だったりする可能性があります。
- 長期的な資産構築を目指す場合
- コンテンツマーケティング(SEO)、オウンドメディア運営、SNSアカウント育成など、時間をかけて信頼関係やブランド力を築く施策が中心となります。
- 成果が出るまでに時間はかかりますが、一度構築できれば安定的なリード獲得が見込めるようになります。
理想的には、短期的な施策と長期的な施策をバランス良く組み合わせたポートフォリオを組むことが望ましいでしょう。
リード獲得を成功させる5つの重要ポイント:成果を最大化する実践ノウハウ
効果的なリード獲得方法を選んだとしても、その実行プロセスでつまずいてしまっては意味がありません。
ここでは、リード獲得の成果を最大化するために押さえておくべき5つの重要なポイントを、実践的なノウハウと共にご紹介します。
1.明確な目標(KGI/KPI)設定と効果測定の仕組み
リード獲得活動を始める前に、具体的な目標を設定することが不可欠です。
最終的な目標(KGI: Key Goal Indicator、例:売上〇〇円、成約数〇〇件)と、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を明確にしましょう。
リード獲得における主要KPI例(CPL, CPA, CV数など)
リード獲得に関連する主要なKPIには、以下のようなものがあります。
- リード数
獲得した見込み顧客の総数。 - コンバージョン数(CV数)
資料請求、問い合わせ、セミナー申し込みなど、目標とするアクションを完了した数。 - コンバージョン率(CVR)
Webサイト訪問者や広告表示回数などに対するコンバージョン数の割合。 - リード獲得単価(CPL)
リード1件を獲得するためにかかった費用(コスト÷リード数)。 - 顧客獲得単価(CPA)
顧客1人を獲得するためにかかった費用(コスト÷顧客数)。 - 商談化率
獲得したリードのうち、商談につながった割合。 - 受注率(成約率)
商談のうち、受注(成約)に至った割合。
これらのKPIを設定し、定期的に効果測定を行うことで、施策の有効性を客観的に評価し、改善点を見つけ出すことができます。
Google Analyticsなどの分析ツールを活用し、データを基にしたPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回していくことが成功の鍵です。
| KPI 名称 | 計算式 | 説明 |
|---|---|---|
| リード数 | – | 獲得した見込み顧客の総数 |
| コンバージョン数(CV数) | – | 目標アクション(資料請求、問合せ等)を完了した数 |
| コンバージョン率(CVR) | CV数 ÷ セッション数(または広告表示回数)× 100 | 訪問者等が目標アクションに至った割合 |
| リード獲得単価(CPL) | 総コスト ÷ リード数 | リード1件獲得にかかった費用 |
| 顧客獲得単価(CPA) | 総コスト ÷ 顧客数 | 顧客1人獲得にかかった費用 |
| 商談化率 | 商談数 ÷ リード数 × 100 | リードから商談に進んだ割合 |
| 受注率(成約率) | 受注数 ÷ 商談数 × 100 | 商談から受注に至った割合 |
2.ターゲットを深く理解する:ペルソナとカスタマージャーニー
「誰に」情報を届けたいのか、ターゲット顧客を深く理解することは、あらゆるマーケティング活動の基本です。
前述のペルソナ設定に加えて、「カスタマージャーニーマップ」を作成することをおすすめします。
カスタマージャーニーマップとは、ペルソナが製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入(契約)に至るまでの思考、感情、行動、タッチポイント(接点)を時系列で可視化したものです。
これにより、顧客が各段階でどのような情報を必要とし、どのようなチャネルで接触するのかを具体的に把握でき、より的確なアプローチやコンテンツを提供することが可能になります。
3.質の高いコンテンツ作成【独自ノウハウがCVR向上の鍵】
特にオンラインでのリード獲得において、コンテンツの質は極めて重要です。
ターゲット顧客の課題解決に役立つ、有益で信頼性の高い情報を提供することが基本となります。
しかし、競合も同様に質の高いコンテンツを発信している中で、差別化を図り、読者の心を掴むためには、自社ならではの独自情報やノウハウを盛り込むことが非常に効果的です。
- 自社データや分析結果
「弊社の調査によると」「〇〇ツールを使った分析結果では」といった、具体的なデータに基づく情報は説得力を増します。 - 独自の成功事例・失敗談
「弊社が〇〇で成功した(失敗した)経験から言えることは」といった、リアルな体験談は読者の共感を呼び、信頼につながります。 - 社内の専門家の知見
「弊社の〇〇専門家によると」といった、専門的な視点からの解説は、コンテンツの価値を高めます。
一般的な情報だけでなく、こうした独自性の高い情報を加えることで、「この記事は他とは違う」「この会社は信頼できそうだ」と読者に感じてもらいやすくなり、結果として資料請求や問い合わせといったコンバージョン率(CVR)の向上につながる可能性が高まります。
実際に、一般的なSEOコンテンツよりも、自社のノウハウが具体的に盛り込まれたコンテンツの方が、明らかにCVRが高いという傾向が見られます。
手間はかかりますが、独自情報を積極的に発信していくことが、リード獲得成功の重要な鍵となります。
4.リード獲得単価(CPL/CPA)を意識した施策運用
リード獲得施策を実行する際には、常に費用対効果を意識することが重要です。
特に、リード獲得単価(CPL)や顧客獲得単価(CPA)を注視し、目標とする単価内に収まっているか、施策ごとに比較してどの手法が効率的かを確認しましょう。
CPL/CPAが高すぎる施策は、ターゲティングの見直し、クリエイティブの改善、ランディングページの最適化など、改善策を検討する必要があります。
一方で、CPL/CPAが低くても、その後の商談化率や受注率が低い(=質の低いリードばかり獲得している)場合は、リードの質を高める工夫が必要です。
予算配分を見直し、費用対効果の高い施策にリソースを集中させることで、全体のROI(投資対効果)を最大化することを目指しましょう。
5.適切なツール(CRM/SFA/MA)の活用とデータ分析
リード獲得から育成、顧客管理までの一連のプロセスを効率的に進めるためには、適切なツールの活用が不可欠です。
- CRM (Customer Relationship Management)
顧客情報を一元管理し、顧客との関係性を維持・向上させるためのツール。リード情報、対応履歴、商談状況などを記録・管理できます。 - SFA (Sales Force Automation)
営業活動を支援するためのツール。商談管理、案件管理、予実管理、日報作成などの機能を持ち、営業プロセスの効率化や可視化を実現します。 - MA (Marketing Automation)
マーケティング活動を自動化・効率化するためのツール。リード情報の獲得・管理、メール配信、スコアリング、Web行動追跡などの機能を持ち、リードナーチャリングを効率的に行えます。
これらのツールを導入し、蓄積されたデータを分析することで、顧客理解を深め、よりパーソナライズされたアプローチや、効果的な施策改善を行うことが可能になります。
【BtoB特化】質の高いリード獲得戦略:最新トレンド「ABM」とは?
BtoBマーケティング、特に大企業をターゲットとする場合、従来の不特定多数に向けたリードジェネレーションだけでは、質の高いリードを獲得し、成果につなげることが難しくなってきています。
そこで注目されているのが、「ABM(アカウントベースドマーケティング)」という比較的新しい戦略です。
ここでは、BtoBリード獲得における最新トレンドとしてABMを解説し、競合との差別化を図るためのヒントを提供します。
なぜ今、BtoBでABM(アカウントベースドマーケティング)が重要なのか?
従来のリードジェネレーションは、広く網をかけてリードを獲得し、その中から有望なものを選別していく「量」を重視するアプローチでした。
しかし、Web上に情報が溢れ、顧客自身が情報収集を行うようになった現代では、この手法だけでは以下のような課題が生じやすくなっています。
- ノイズが多い
ターゲット外のリードが多く含まれ、営業効率が低下する。 - コンテンツが刺さらない
大衆向けのコンテンツでは、特定の企業の課題やニーズに響きにくい。 - 大手企業攻略の難しさ
意思決定プロセスが複雑な大手企業に対して、画一的なアプローチでは効果が出にくい。
こうした背景から、特定のターゲット企業(アカウント)を明確に定め、その企業に最適化されたアプローチを行うABMが重要視されるようになりました。
ABMは、「質」を重視し、リソースを集中させることで、より効率的かつ効果的に優良顧客を獲得することを目指す戦略です。
ABMの基本的な考え方とメリット・デメリット
ABMは、マーケティング部門と営業部門が連携し、ターゲットとする企業(アカウント)を特定し、そのアカウント内の主要な意思決定者に対して、パーソナライズされたメッセージやコンテンツを届け、関係性を構築していくアプローチです。
メリット
- 高いROI
リソースを有望なアカウントに集中させるため、無駄なコストを削減し、投資対効果を高めやすい。 - 営業とマーケティングの連携強化
共通のターゲットアカウントを持つことで、両部門の連携が促進され、一貫したアプローチが可能になる。 - 顧客エンゲージメント向上
ターゲット企業に合わせてパーソナライズされたアプローチを行うため、顧客の関心を引きつけやすく、深い関係性を構築できる。 - 質の高いリード獲得
自社にとって価値の高い企業に絞ってアプローチするため、獲得できるリードの質が高い。
デメリット
- ターゲット選定の重要性
ターゲットアカウントの選定を誤ると、大きな機会損失につながる可能性がある。 - リソースの集中
特定のアカウントにリソースを集中させるため、広範な市場へのアプローチが手薄になる可能性がある。 - 準備と実行に手間がかかる
アカウントごとの調査やコンテンツ作成、個別アプローチが必要となるため、従来のリードジェネレーションよりも手間がかかる。 - ツールの活用が推奨される
効果的にABMを実践するには、専用ツールなどの導入が推奨される場合が多い。
ABMの実践ステップ:ターゲット選定からアプローチまで
ABMを実践するための基本的なステップは以下の通りです。
- ターゲットアカウントの選定
- 自社にとって理想的な顧客像(ICP: Ideal Customer Profile)を定義する。
- 市場データや自社データに基づき、ICPに合致するターゲットアカウントリストを作成する。企業規模、業種、地域、導入済みテクノロジーなどを考慮する。
- アカウント内の主要人物の特定
- ターゲットアカウント内の意思決定者や、製品・サービス導入に影響力を持つ担当者を特定する(キーパーソンマッピング)。
- アカウント情報の収集と分析
- ターゲットアカウントのビジネス課題、組織構造、競合状況などを詳細に調査・分析する。
- パーソナライズされたコンテンツとメッセージの作成
- 収集した情報に基づき、ターゲットアカウントや主要人物の特定のニーズや課題に響くようなコンテンツ(事例、ホワイトペーパー、提案書など)やメッセージを作成する。
- マルチチャネルでのアプローチ
- メール、電話、Web広告、SNS(特にLinkedIn)、ダイレクトメール、イベントなど、複数のチャネルを組み合わせて、ターゲットアカウント内の主要人物にアプローチする。
- 営業とマーケティングの連携
- マーケティング活動の状況や得られたインサイトを営業部門と密に共有し、連携してアプローチを進める。
- 効果測定と改善
- アカウントごとのエンゲージメント(Webサイト訪問、コンテンツ閲覧、問い合わせなど)、商談化率、受注率などを測定し、アプローチ方法やコンテンツを継続的に改善する。
【事例】ABM導入で成果を上げた企業の取り組み
あるBtoB SaaS企業では、従来のリードジェネレーション施策に行き詰まりを感じていました。
そこで、特定の業界(例:製造業)の大手企業をターゲットとするABM戦略を導入。
まず、ターゲットアカウントリストを作成し、各企業の抱えるであろう課題を仮説立て、それに対応する業界特化型のホワイトペーパーや導入事例を作成しました。
次に、MAツールを活用し、ターゲットアカウントからのWebサイトアクセスを検知。
アクセスがあった企業の担当者に対して、パーソナライズされたメールを送付したり、LinkedIn広告で関連コンテンツを表示したりするアプローチを実施。
営業部門とも連携し、マーケティング活動で得られたインサイトを共有しながら、タイミングを見計らって架電やオンラインデモの提案を行いました。
その結果、導入前と比較して、ターゲットアカウントからの問い合わせ数が2.5倍に増加し、商談化率も30%向上しました。
CPLは若干上昇したものの、質の高いリードが増加したことで、最終的な受注額は1.8倍となり、ROIの大幅な改善につながりました。
このように、ABMはBtoB、特に大手企業攻略において非常に有効な戦略となり得ます。
獲得したリードを無駄にしない!リードナーチャリングの重要性
リードを獲得することは、あくまでスタートラインに立ったに過ぎません。
獲得したリードをそのまま放置していては、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまいます。
獲得したリードを実際の顧客へと育成していくプロセス、「リードナーチャリング」が極めて重要になります。
リードナーチャリングとは?目的と基本的な流れ
リードナーチャリング(Lead Nurturing)とは、「見込み顧客育成」と訳され、獲得したリードに対して継続的にコミュニケーションを取り、関係性を構築・深化させながら、徐々に購買意欲を高めていくマーケティング活動のことです。
目的
- リードとの関係性を維持・強化する。
- 自社製品やサービスへの理解を深めてもらう。
- 信頼感を醸成する。
- 購買意欲を適切なタイミングで高める。
- 最終的に質の高い商談(SQL)へと引き上げる。
基本的な流れ
- セグメンテーション
獲得したリードを、属性(業種、役職など)や行動履歴(Webサイト閲覧、資料ダウンロードなど)、興味関心に基づいてグループ分け(セグメント化)する。 - コンテンツ提供
各セグメントのニーズや興味に合わせて、適切なタイミングで有益なコンテンツ(ブログ記事、事例、セミナー案内、製品情報など)を提供する。 - コミュニケーション
メール、電話、SNSなどを通じて、一方的な情報提供だけでなく、双方向のコミュニケーションを図る。 - スコアリング
リードの行動(メール開封、クリック、Webサイト訪問など)や属性に基づいて点数(スコア)を付け、購買意欲の高さを測る。 - 営業への引き渡し
スコアが一定の基準に達したリード(SQL)を、営業部門に引き渡す。
効果的なリードナーチャリングの手法(メール、MA活用など)
リードナーチャリングには様々な手法がありますが、代表的なものをいくつかご紹介します。
- メールマーケティング
- ステップメール
あらかじめ設定したシナリオに基づき、段階的にメールを自動配信する。リードの検討段階に合わせて情報を提供できる。 - セグメント別メルマガ
リードの興味関心に合わせて内容を変えたメールマガジンを配信する。 - パーソナライズメール
リードの名前や会社名を記載したり、過去の行動履歴に基づいたコンテンツを推奨したりする。
- ステップメール
- マーケティングオートメーション(MA)の活用
- メール配信の自動化、リードスコアリング、Web行動追跡、セグメンテーションなどを効率的に行うことができる。
- 適切なタイミングで、適切な相手に、適切なコンテンツを届けることを支援する。
- リターゲティング広告
一度Webサイトを訪問したリードに対して、再度広告を表示する。 - インサイドセールス
電話やメール、Web会議ツールなどを活用し、非対面でリードとのコミュニケーションを図り、関係構築や課題ヒアリングを行う。 - 限定コンテンツの提供
特定のリードに対して、ウェビナーのアーカイブ動画や、より詳細な資料などを限定的に提供する。
これらの手法を組み合わせ、リードの状況に合わせて継続的にアプローチしていくことが重要です。
リードクオリフィケーション:営業に引き渡すリードの見極め方
リードナーチャリングによって育成されたリードの中から、実際に営業担当者がアプローチすべき、購買意欲の高いリードを選別するプロセスが「リードクオリフィケーション」です。
見極めのための代表的な手法としては、以下のようなものがあります。
- リードスコアリング
前述の通り、リードの属性や行動に基づいて点数を付け、一定のスコアを超えたリードを営業対象とする。 - BANT条件の確認
営業が商談を進める上で重要とされる以下の4つの要素を確認する。- Budget(予算)
導入に必要な予算を持っているか? - Authority(決裁権)
導入の決定権を持っているか? - Needs(必要性)
製品やサービスに対する明確なニーズがあるか? - Timeframe(導入時期)
具体的な導入時期を検討しているか?
- Budget(予算)
- インサイドセールスによるヒアリング
電話などで直接ヒアリングを行い、課題やニーズ、導入意欲などを確認する。
これらの基準を基に、マーケティング部門と営業部門が連携して、どのリードをどのタイミングで営業に引き渡すかのルールを明確にしておくことが、スムーズな連携と成果向上につながります。
リード獲得を加速させる!おすすめツール&サービス紹介
リード獲得から育成、管理までの一連のプロセスを効率化し、成果を最大化するためには、適切なツールの活用が欠かせません。
ここでは、リード獲得活動を支援する代表的なツールやサービスをご紹介します。
CRM/SFAツール:顧客情報の一元管理と営業活動支援
- CRM (顧客関係管理) ツール
- 顧客やリードの基本情報、対応履歴、購買履歴などを一元管理するツール。
- 顧客理解を深め、長期的な関係構築を支援します。
- 代表例: Salesforce Sales Cloud, HubSpot CRM, Zoho CRM, kintone など。
- SFA (営業支援システム) ツール
- 営業担当者の活動を支援し、効率化を図るツール。
- 商談管理、案件管理、スケジュール管理、予実管理、レポート作成などの機能があります。
- 代表例: Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, Senses, eセールスマネージャー など。
CRMとSFAは機能が重複する部分も多く、一体型のツールも増えています。
これらのツールを活用することで、リード情報を効率的に管理し、営業活動との連携をスムーズに行うことができます。
MAツール:マーケティング活動の自動化と効率化
- MA (マーケティングオートメーション) ツール
- リード獲得、リードナーチャリング、スコアリング、メール配信、キャンペーン管理など、マーケティング活動の多くを自動化・効率化するツール。
- パーソナライズされたコミュニケーションを実現し、リード育成を効果的に進めることができます。
- 代表例
- HubSpot Marketing Hub
- Adobe Marketo Engage
- Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot)
- SATORI
MAツールは、特に多くのリードを扱う場合や、複雑なナーチャリングシナリオを実行したい場合に有効です。
その他(フォーム作成、Web接客、ABMツールなど)
上記以外にも、リード獲得を支援する様々なツールがあります。
- フォーム作成ツール
Webサイトに設置する問い合わせフォームや資料請求フォームを簡単に作成・管理できるツール。
(例: Google Forms, formrun, Tayori) - Web接客ツール
Webサイト訪問者に対して、チャットボットやポップアップ表示などで適切なタイミングで話しかけ、問い合わせや資料請求を促すツール。
(例: Chamo, KARTE, Intercom) - ABMツール
ターゲットアカウントの特定、アカウント情報の収集、パーソナライズされたキャンペーン実行などを支援する、ABMに特化したツール。
(例: Demandbase, Terminus, FORCAS) - オンライン商談ツール
Web会議システムを利用して、遠隔地のリードとも対面に近い形で商談を行えるツール。
(例: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, BellFace) - データ分析ツール
Webサイトのアクセス状況や広告効果などを分析するツール。
(例: Google Analytics, Adobe Analytics)
自社の課題や目的に合わせて、これらのツールを組み合わせて活用することを検討しましょう。
リード獲得支援サービス・コンサルティング
社内にノウハウやリソースがない場合、リード獲得戦略の立案から実行までを支援してくれる外部のサービスやコンサルティングを活用することも有効な選択肢です。
- リード獲得代行
テレアポ代行、広告運用代行、コンテンツ作成代行など、特定の施策を代行してくれるサービス。 - マーケティングコンサルティング
リード獲得戦略全体の設計、KPI設定、ツール導入支援、効果測定などを支援してくれるサービス。
専門家の知見を借りることで、より早く、確実に成果を出すことが期待できます。
自社ノウハウを活かしたリード獲得成功事例紹介
ここでは、一般的な手法だけでなく、自社ならではのノウハウやデータを活用することで、リード獲得に成功した具体的な事例をご紹介します。
事例1:コンテンツSEOと独自データ活用で問い合わせ数を3倍にした方法
課題
あるWeb制作会社では、ブログ記事からの問い合わせ数が伸び悩んでいました。
一般的なSEO対策は行っていたものの、競合との差別化が図れず、埋もれてしまっている状況でした。
施策
- 独自データの収集・分析
これまで制作した数百のWebサイトのアクセスデータやコンバージョンデータを分析し、「コンバージョンしやすいWebサイトデザインの共通点」「特定の業種で効果の高いCTAボタンの配置」といった独自の知見を抽出しました。 - 独自ノウハウを盛り込んだコンテンツ作成
分析結果や社内のWebデザイナー、マーケターの知見を基に、「【独自データ公開】問い合わせが3倍になるWebデザインの法則」「製造業向け:リード獲得を最大化するWebサイト設計術」といった、具体的で独自性の高いブログ記事を作成しました。
記事内には、分析データを示すグラフや、具体的な改善前後の比較などを盛り込みました。 - SEO対策の強化
独自性の高いコンテンツに合わせて、関連キーワードの再選定や内部リンクの最適化を行いました。
結果
独自ノウハウを盛り込んだ記事は、ターゲット顧客からの関心が高く、検索エンジンからの評価も向上しました。
結果として、ブログ経由での月間問い合わせ数が施策実施前の3倍に増加し、記事からのCVRも平均で1.5倍になりました。
事例2:ウェビナーとMA連携で質の高いリード獲得単価を50%削減
課題
あるITツールベンダーでは、ウェビナーを開催しても、その後の商談につながるリードが少なく、リード獲得単価(CPL)が高いことが課題でした。
施策
- MAツールとの連携強化
ウェビナー申し込みフォームとMAツールを連携させ、申込者の属性情報(役職、課題感など)を取得できるようにしました。 - パーソナライズされたフォローアップ
ウェビナー参加者の属性や、ウェビナー中のアンケート回答、終了後の行動(資料ダウンロードなど)に応じて、MAツールでナーチャリングシナリオを分岐。関連性の高い追加情報や、個別の課題に合わせたメールを自動送信するように設定しました。 - スコアリングによる絞り込み
MAツールでリードの行動をスコアリングし、特にエンゲージメントの高いリード(例:関連資料を複数ダウンロード、価格ページを閲覧)を特定し、優先的にインサイドセールスがフォローアップする体制を構築しました。
結果
リード一人ひとりに対して、より適切な情報提供とフォローアップが可能になったことで、リードの質が向上。
商談化率が2倍になり、結果的に質の高いリード(SQL)の獲得単価を50%削減することに成功しました。
事例3:ABMアプローチで特定の大手企業からのリード獲得に成功
課題
あるコンサルティング会社では、特定の大手企業を新規クライアントとして開拓したいと考えていましたが、従来のアプローチではなかなか接点を持てずにいました。
施策
- ターゲットアカウントの徹底分析
ターゲットとする大手企業の公開情報(IR情報、中期経営計画、ニュースリリースなど)を徹底的に分析し、彼らが現在抱えているであろう経営課題や戦略目標を特定しました。 - パーソナライズされた提案コンテンツ作成
特定された課題に対し、自社のコンサルティングサービスがどのように貢献できるかを具体的に示した、その企業専用の簡易提案資料や課題解決事例を作成しました。 - キーパーソンへの多角的アプローチ
LinkedInなどを活用してターゲット企業内の関連部署のキーパーソンを特定。作成したパーソナルコンテンツを添付した個別メールを送付したり、関連性の高いセミナーへ招待したりするなど、複数のチャネルからアプローチを行いました。役員層には、手書きの手紙を送付するといったアナログな手法も組み合わせました。
結果
画一的なアプローチではなく、自社の課題に深く踏み込んだ提案を行ったことで、ターゲット企業のキーパーソンの関心を引くことに成功。
これまで接点のなかった複数のキーパーソンとの面談設定につながり、最終的に大型のコンサルティング契約を獲得することができました。
これは、ABMによるターゲット集中とパーソナライズアプローチの成功例と言えます。
まとめ:自社に最適なリード獲得方法を見つけ、継続的な成長を実現しよう
この記事では、リード獲得の基本から、オンライン・オフラインの具体的な手法20選、BtoB特化のABM戦略、成功のポイント、役立つツール、そして独自ノウハウを活かした事例まで、幅広く解説してきました。
リード獲得は、企業の成長に不可欠な活動ですが、その方法は一つではありません。
重要なのは、自社のターゲット顧客、ビジネスモデル、予算、リソース、そして商材の特性を深く理解し、最適な手法を戦略的に選択・組み合わせることです。
そして、単にリードを獲得するだけでなく、その後のナーチャリングプロセスを見据え、質の高いリードを育成し、最終的な成果につなげる視点を持つことが大切です。
また、競合との差別化を図るためには、自社ならではのデータやノウハウといった独自情報を積極的に活用することが、顧客の信頼を得てコンバージョン率を高める鍵となります。
リード獲得は、一度戦略を立てて終わりではありません。
明確なKPIを設定し、効果測定を行いながら、常にPDCAサイクルを回し、改善を続けていくことが、継続的な成果を生み出すためには不可欠です。
この記事でご紹介した情報を参考に、ぜひ貴社に最適なリード獲得戦略を見つけ出し、実践してみてください。
効果的なリード獲得を通じて、ビジネスの持続的な成長を実現されることを願っています。